要約
基本
「生物と無生物のあいだ」とは、生物学者の福岡伸一氏によるエッセーである。
(S-CLIP社の創業メンバーの出身グループライン名は「成年と未成年のあいだ」)
生物と無生物の違いを熱力学や化学で語るパートと研究を語るパートが錯綜する。
生物と無生物について
最後の最後に夢オチ的なオチが待っている。
「本は後書きから読め」とはよく言ったもの。
私たちは、自然の流れの前に跪く以外に、そして生命のありようをただ記述すること以外に、なすすべはないものである。
福岡伸一、生物と無生物のあいだ、p.285、講談社現代新書(2007)
「ただ跪くしかない」と言われたら、「はあ、そうですか」というしかないだろう。
著者によれば、生命を次の一文で再定義している。
生命とは動的平衡(ダイナミック・イクイリブリアム)にある流れである
福岡伸一、生物と無生物のあいだ、p.167、講談社現代新書(2007)
原子や分子が入れ替わりながらも全体としては平衡(変化がないように見える)ということで、同じ状態を維持するメカニズムとして次のように説明している。
生命とは動的平衡にある流れである。生命を構成するタンパク質は作られる際から壊される。それがその秩序を維持するための唯一の方法であった。しかし、なぜ生命は絶え間なく壊され続けながらも、もとの平衡を維持することができるのだろうか。その答えはタンパク質のかたちが体現している相補性にある。生命は、その内部に張り巡らされたかたちの相補性によって支えられており、その相補性によって、絶え間のない流れの中で動的な平衡状態を保ちえているのである。
福岡伸一、生物と無生物のあいだ、p.178、講談社現代新書(2007)
例えば、DNAの二重鎖がペアの配列を記憶しているので、その相補性がかたちを保持しているということで、その見方は初めてだったので面白かった。
他にもシュレーディンガーの「生命とは何か」を引用しながら秩序の象徴としての「負のエントロピー」「ネゲントロピー」で生命の不思議さを説明したりするが、ある遺伝子を一つ失ったマウスがピンピンしていたエピソードを踏まえ、最終的な結論は以下であった。
私たちは遺伝子をひとつ失ったマウスに何事も起こらなかったことに落胆するのではなく、何事も起こらなかったことに驚愕すべきなのである。動的な平衡がもつ、やわらかな適応力となめらかな復元力の大きさにこそ感嘆すべきなのだ。結局、私たちが明らかにできたことは、生命を機械的に、操作的に扱うことの不可能性だったのである。
福岡伸一、生物と無生物のあいだ、pp.271-272、講談社現代新書(2007)
「生命は機械的に扱えないよ」ということで生物と無生物の違いを明らかにしているのも視点が斬新だった。
人工生命のような構成論的なアプローチもあるが、この本は博物学的な視点が豊富な印象を受けたのだった。
研究について
研究者のしんどい生活にや魔がさす瞬間についてのネガティブな記述が多い。
例えば、日本では偉人として有名な医師の野口英世が抱えていた闇について触れている。
パスツールやコッホの業績は時の試練に耐えたが、野口の仕事はそうならなかった。数々の病原体の正体を突き止めたという野口の主張のほとんどは、今では間違ったものとしてまったく顧みられていない。彼の論文は、暗い図書館の黴臭い書庫のどこかの一隅に、歴史の澱と化して沈み、ほこりのかぶる胸像とともに完全に忘れ去られたものとなった。野口の研究は単なる錯誤だったのか、あるいは故意に研究データを捏造したものなのか、はたまた自己欺瞞によって何が本当なのか見極められなくなった果てのものなのか、それは今となっては確かめるすべがない。けれども彼が、どこの馬の骨とも知れぬ自分を拾ってくれた畏敬すべき師フレクスナーの恩義と期待に対し、過剰に反応するとともに、自分を冷遇した日本のアカデミズムを見返してやりたいという過大な気負いに常にさいなまれていたことだけは間違いないはずだ。その意味で彼は典型的な日本人であり続けたといえるのである。
福岡伸一、生物と無生物のあいだ、p.21、講談社現代新書(2007)
一方、遺伝子の本体がDNAであると実験から喝破した、野口と同様にロックフェラーと縁のあったエイブリーについて肯定的に描いている。
ロックフェラー大学の人々にエイブリーのことを語らせると、そこには不思議な熱が宿る。誰もがエイブリーにノーベル賞が与えられなかったことを科学史上最も不当なことだと語り、ワトソンとクリックはエイブリーの肩に乗った不遜な子供たちに過ぎないとののしる。皆がエイブリーを自分に引き寄せて、自分だけのアイドルにしたがる理由は他にもあるような気がする。早熟な天才だけが、あるいは若い一時期だけが、研究上のクリエイティビティを発揮できる唯一のチャンスであると喧伝される科学界にあって、遅咲きのエイブリーはここでもある種の慰撫をもたらしてくれるアンサング・ヒーローなのだ。
福岡伸一、生物と無生物のあいだ、p.57、講談社現代新書(2007)
研究者と研究環境については、ピアレビューにおける誘惑(p.103)や、海外ではポスドクを「研究室の奴隷(ラブ・スレイブ lab slave)呼ぶ(ブラック)ジョークがあるという話など、金がなく競争の激しい中でも真理を追求する崇高さが描かれる。
「生命や自然の神秘を探究したい」というピュアな好奇心と「研究者として成功してやる」という功名心のせめぎ合いである。
考察
本の帯にあるような「文才」を感じるエッセーであった。
実際に生命や自然を観察する経験を積まないと実感が湧かない部分もあるだろう。
物理や化学の基礎知識がないとピンとこない部分もあるが、それも含めて難易度の高い書籍ではある。
「生物と無生物のあいだ」が結局のところ何なのかが最後までよくわからない点は残念だったが、まだ私たちの地球や宇宙にはわからないことがあるのだという捉え方をすれば、普段何気なく見ている自然の風景が輝いて見えるようになる本ともいえる。
「生命とは何か」と疑問に思った人や生き物・生命に興味のある人は(ブックオフなどで)一度手にとってみてもいいだろう。


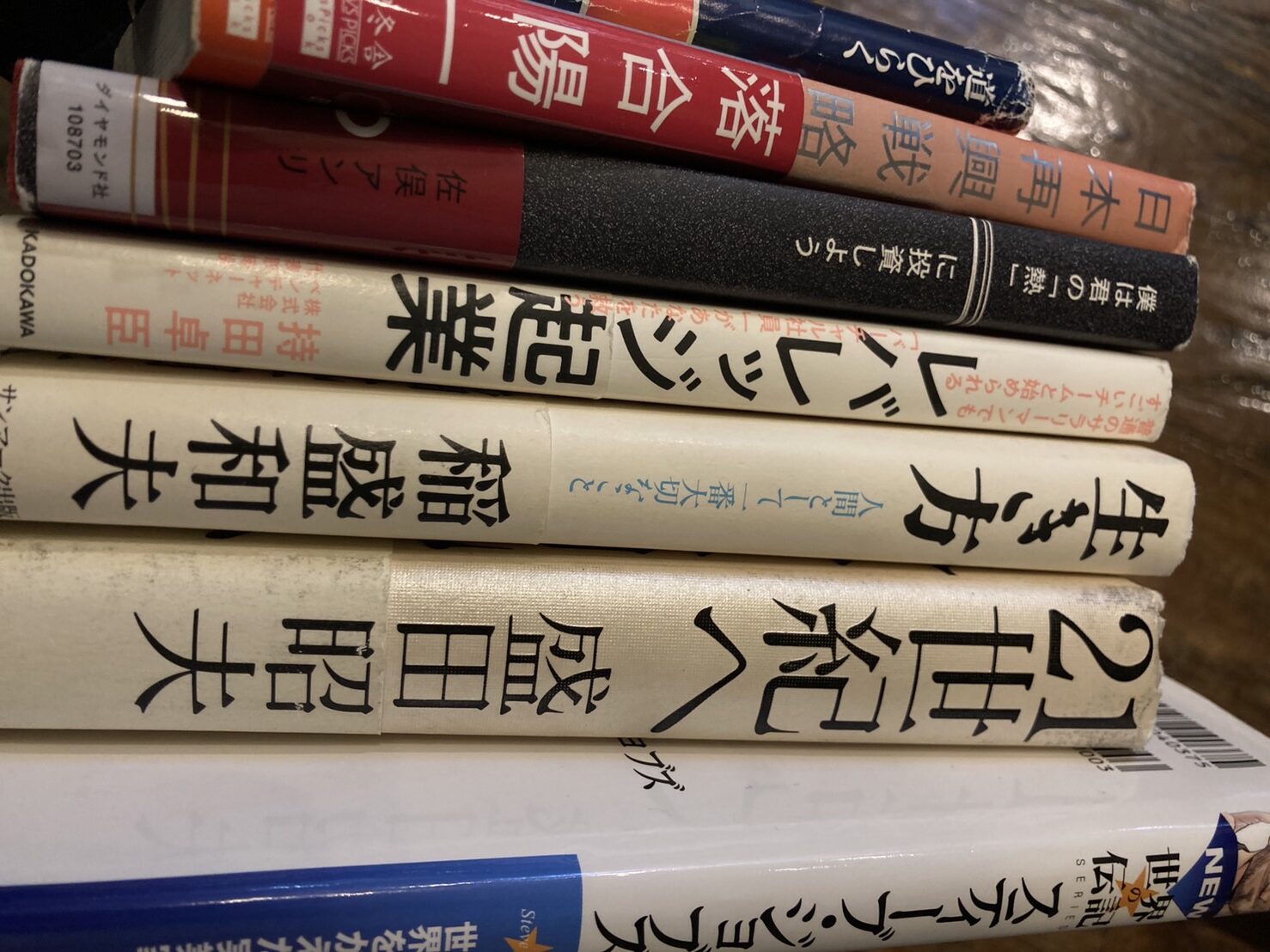
コメント